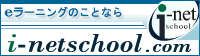※当コラムは、企業人事に従事される方にはおなじみの「月刊 人事マネジメント」に寄稿させていただいた原稿を一部加工修正したものです。
◇コンプライアンス経営、リスクマネジメントの実務書
この2025年7月末に「事業部長になるための経営の基礎Ⅱ:コンプライアンス経営から危機管理、不正・不祥事への対処までがわかる本」(生産性出版)という著書を、この仕事、またこの分野における先達・角渕渉氏(アクア ナレッジ ファクトリ株式会社)と上梓することになった。
我々は20年以上にわたってコンプライアンス、リスクマネジメント教育に取り組んできたが、本書はその成果をまとめたものと言えよう。
◇企業不祥事の歴史とコンプライアンス経営の厳格化
なお、当該期間は、次々に発覚する企業不祥事の歴史でもあった。だが別の観点からみると、20年以上走り続けてきた企業人にとって、この期間は現に日本政府が掲げる社会の実現を目指して、企業のコンプライアンス経営を推進してきた歴史でもあるはずだ。
3つの社会の実現:「ワーク・ライフ・バランスが実現された社会」
(1)就労による経済的自立が可能な社会
(2)健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会
(3)多様な働き方・生き方が選択できる社会
特に昨今、労働施策総合推進法の改正により、職場におけるハラスメント対策が令和2年6月1日から大企業の義務になり、令和4年4月1日から中小企業の義務になった。
事業主に対策が義務づけられたハラスメントには、20数年前にはそんな言葉すらなかった“パワハラ”も当然に含まれている。そして更に、これからはAIやロボットと協業していく時代である。
◇科学技術の進歩と人間の本質、そして教育
先日、友人とこんな話をした。
「科学技術の進歩は、人間の本質を善い方向に変えたか」
それに対して、友人は少し考えてからこう答えた。
「人間の本質は今も昔も変わらないのではないか。変わりうるとすれば、それは教育によってのみだろう」友人のこの答えに、筆者も深く頷くしかなかった。
そうである、人間の本質は今も昔も変わらない。
だが、時代環境の変化をもとらえた適切な教育のみが人間を成長させ、成熟させ、企業や社会により善く適応させていくのである。
◇日本型コンプライアンスとその特殊性、教育の重要性
だとすれば、今後日系企業おける日本型コンプライアンス教育というものは、益々その重要性が高まるはずだ。
欧米型とは異なる日本型コンプライアンスについては本誌でも以前に述べ、また新刊でも詳しく述べるが、日本型は新社会人に倫理規範意識を植え付けることから、その教育ははじまる。
そしてAIやロボットと協業していく時代、新たなリスクが次々と発現し、その対策が求められることは、火を見るよりも明らかだ。
そんな来し方行く末を見すえながら、我々はコンプライアンス、リスクマネジメント教育に携わり続けているわけであるが、その現場において昔も今も変わらないことがひとつある。
◇事業部長を目指す企業人にとっての基本図書
それは、研修終了後などに受講者から「このあと、どんな勉強をすればよいでしょうか」「良い参考書を紹介していただけませんか」という要望をいただくことだ。
コンプライアンス経営の取り組みが始まった20年前なら基礎から実践までの一貫した解説を含む良書が数多く出版されていたが、最近は高度な研究書か初心者向けのゼロからの解説書が多く、受講者にお勧めできる書物が意外に少ない。
そこで「書店にないのなら我々で書いてしまおう」という話になり執筆した原稿が、前著「事業部長になるための経営の基礎」の姉妹本として、先日発売した「事業部長になるための経営の基礎II: コンプライアンス経営から危機管理、不正・不祥事への対処までがわかる本」(生産性出版)だ。
多大なリスクと隣り合わせの事業部長がこの分野において備えるべき知見は多岐にわたるが、本誌ではなるべくコンパクトに、事業部長を目指す企業人にとっての基本図書、コンプライアンス部門やリスクマネジメント部門のスタッフの方々の参考文献として解説を試みている。
アイベックス・ネットワーク 代表 新井 健一