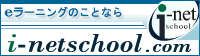※当コラムは、企業人事に従事される方にはおなじみの「月刊 人事マネジメント」に特別寄稿させていただいた原稿を一部加工修正したものです。
◇人的資本経営とリスキリング
「リスキリング」、経団連、経産省などの積極的な発信により、職業能力の再開発、再教育を意味するこの言葉や取組みが、企業に浸透しつつある。
だが、当の企業、その社員として、「リ」「スキリング」という言葉は聞いたことがある一方、次の問いに適切に答え、実際に動けている人材は少ないのではないか。
「なぜいま、会社員にリスキリングが叫ばれるのか」
「どのような職業で、具体的にどのようなリスキリングが必要なのか」
「『わたし』はリスキリングにどう対応すればよいのか」
ここでは、リスキリングが言われるようになった背景および人生100年副業(複業)時代に会社員が目指すべき「次の」働き方を考え、方向性を見い出すための考察を試みたい。
まず、遡ること1990年はじめのバブル崩壊以降、それまで日本型雇用の象徴であった終身雇用、年功序列型賃金が崩壊すると言われたが、それでも日系企業に勤める社員の平均勤続年数は微増ながら伸び続けていた。
だが、ここにきて日本の雇用管理は大きく変化しており、株式会社マイナビ「働き方、副業・兼業に関するレポート(2020年)」および株式会社ライボ「2022年 副業・兼業に関する実態調査」は、企業における副業・兼業に関する実態を次のようにまとめている。
■働き方、副業・兼業に関するレポート(2020年) 現在、副業・兼業を認めている企業は全体で49.6%、将来的に認める・拡充する予定の企業は計57.0%*となった。 *将来的に認める・拡充する予定の企業(57.0%):「現在認められており、将来的にも拡充する予定(19.4%)」+「現在一部認められているが、将来的には拡充する予定(22.4%)」+「現在は認められていないが、将来的には認められる予定(15.2%)」 副業や兼業を導入している企業の導入理由で最も多いのは「社員の収入を補填するため(43.4%)」だった。 マイナビの調べにつき、一部筆者にて加工 ■2022年 副業・兼業に関する実態調査 現在の副業・兼業実施率について全体の21.6%が「副業・兼業をしている」と回答した。 また「副業・兼業をしている」の回答を”年代別”で見ると、50代が26.7%で最多。更に同じく「副業・兼業をしている」の回答を”本業だけの年収区分”で見ると「200万円未満」が35.3%で最多になった。 副業・兼業を始めたタイミングについては全体の45.5%が「コロナ禍後」と回答し、54.5%が「コロナ禍前」の結果になった。また副業・兼業を始めた時期を見ると、コロナ禍に入ってから副業・兼業を開始した回答者が多いことがわかった。 副業・兼業をしていると回答した143名の”始めた理由”で最も多かったのは、「収入を上げるため」で83.2%となった。また”始めたきっかけ”については「本業だけでは生活が苦しくなった」が44.1%で最多回答になった。 ライボの調べにつき、一部筆者にて加工 このように、ここ10年ほどの経過において、副業・兼業を解禁する企業が増加の一途をたどる中、その流れをコロナが加速したことは調査結果からも読み取ることができる。 一方で、副業・兼業を解禁した企業においても約8割の社員は、本業以外の仕事に従事していないという実態も見えてきた。
企業そして社員双方の意向として、副業・兼業に従事する人材はますます増えていくであろうが、ここで留意しておかなければならないのは「その副業・兼業は、今後のキャリア形成において、プラスになると意図的、戦略的に判断して選び取ったものか、それとも単に時間の切り売りにしか過ぎないか」ということだ。
ある意味、このコロナ禍および日本においては労働力不足の深刻化がブラインドとなっているが、これからAI(人工知能)がますます人間の労働を代替していくことに対し、我々はより意識的になるべきである。
◇AIやロボットにより今後なくなる仕事への自覚
例えば、世界にその名を馳せる戦略コンサルティング会社のシンクタンク部門が、800以上の職業における2000以上の作業を分析した結果、すべての作業が自動化の対象となる職業は全体の5%未満だが、おおよそ60%の職業において、少なくとも3割程度の作業が技術的には代替可能であると報告した。
ちなみに、野村総合研究所と英オックスフォード大学のマイケル・オズボーン准教授らで行った共同研究によれば、今後20年以内に、日本の労働人口の約半分(49%)がAIやロボットにより代替される可能性が高いとしている。
◇キャリア形成における副業・兼業のかしこい選択
労働力人口の減少、深刻なヒト不足が叫ばれている我が国において、当面最もAIの恩恵を受けるのは、他ならぬ日本だと言われているが、果たして全ての働き手がAIの恩恵を受けるのだろうか。
生活のためとはいえ、単に時間の切り売りにしか過ぎない副業・兼業を安易に選択することが、本人のキャリア形成において、どれほどマイナスに働くかということを自覚しておく必要はないだろうか。
そしてもう一つ、現に日系企業で働く会社員、その多くは今後のキャリア形成においてプラスになるような副業・兼業を選択することが難しいということも認識しておく必要もあるだろう。
コロナにより急速に普及したテレワークだが、このような働き方に対して適切な人事評価を行うべく、ジョブ型の働き方が脚光を浴びることになった。
ジョブ型とは、企業と求職者が雇用契約を締結する段階で、ジョブの範囲とポストが明記さて、固定されている欧米企業では標準的な働き方だ。そして欧米人は、常に特定の職種やポストでキャリアを積む。
◇日本型と欧米型の働き方、今後のキャリア選択・形成
それに対して、メンバーシップ型の働き方をとってきた日系企業では、現に同じ職種やポストで働いていたとしても、それまでの職務経歴がてんでバラバラなため、転職はもちろん副業や兼業においても、それまでのキャリアに応じた標準的なジョブというものを提示することができない。
実際、このことも8割にのぼる会社員の副業・兼業選択、しかも今後のキャリア形成においてプラスになるような選択を難しくしていることは間違いないと言えるだろう。
このように、日本においてコロナが加速した労働市場の変化を踏まえ、自らのキャリア形成において、プラスとなるような副業・兼業選択に悩む会社員は相当数にのぼると筆者は考える。
そして、そのような人材、会社員という働き方に寄り添いサポートすべく、先ずは当該人材のキャリア形成においてプラスとなるような仕事や仕事から得られる知識、スキル、経験は何かを明らかにし、副業・兼業選択に活かすのは勿論のこと、必要に応じて前向き、効率的な学び直しを支援する一連の教育プログラムが必要となるだろう。
◇成長するリカレント教育という市場
では、そのような教育の一環として、昨今注目されるリカレント教育市場に転じてみたい。
リカレント教育とは、社会人が、キャリアチェンジや社会環境の変化に応じて必要となるスキルを、本格的に学び直すための学習サービスである。
なお、対象となる学習プログラムは、大学が社会人を対象に提供する履修証明プログラム、科目等履修生制度、大学院の修士課程・専門職学位課程、および民間事業者が社会人を対象に提供する「リカレント教育」に資するものである。
なお、ここでリカレント市場に関する見解につき、「ResedEd(リシード)教育業界ニュース」からその一部を引用する。
2021年度のリカレント教育市場規模は、前年度比7.1%増の467億円を見込む。時代の変化に即した知識、スキル習得の必要性が強まっていることや、政府が「リカレント教育」の拡充を進める動きがあること、企業がジョブ型の人材採用や人材育成へシフトを進めつつあることから、リカレント教育市場に注目の高まる環境が創出されている。
2021年度はコロナ禍によって、大学提供のプログラムの大半は集客面に苦戦が強いられた。
一方で、在宅勤務・リモートワークの広がりやDXの加速化等を背景に自身のキャリアプランを見直す個人が増加。これにより、民間事業者が提供するプログラムは、特にオンラインで完結する教育プログラムが大きく伸びた。特にIT、デジタル系人材に関するプログラムが好調。
(中略)
今後の大きな課題は、学び直ししたことによる転職やキャリアチェンジにつながる人材流動が日本国内ではあまり進んでいないこと。今後は、社会的風土の醸成や制度面での整備が求められる。
2022年度のリカレント教育市場規模は、前年度比4.9%増の490億円が予測されている。
今後は、個人が自身のキャリアプランを見直す動きが強まる傾向や、企業・社会で求められるスキルの変化、政府による「リカレント教育」拡充を進める動き等により、リカレント教育市場の需要は高まりを続けていく見通し。
このように、リカレント教育は、その後の転職やキャリアチェンジに関わる社会的風土の醸成や制度面での整備などに課題があるとしつつ、確かな時代のニーズをとらえ、今後ますます成長が見込まれる分野であることは間違いない。
ここで、冒頭に述べたリスキリングとリカレント教育の違いについて触れておこう。
リスキリングとは、職業能力の再開発、再教育のことを意味し(再掲)、時代の文脈に則して言えば「市場の変化に対応すべく新しい職種・業務に就くこと」や「現職で求められるスキルの変化に適応し、持続的に価値を創出すること」を目的に、新しいスキルや技術の習得を推進する全般的な取組みを指す。
そして特に現在、第四次産業革命(IoTやAI、ビッグデータによる技術革新)への対応が強く求められる一方、デジタル技術をビジネスに活用するハイスキル人材の不足が、国家レベルで問題視されている状況である。
したがって、リスキリングによるIoT、AI、データサイエンスなどのスキル開発は、社内人材のデジタル人材化につながるため、官民で注目を集めているのだ。
さて、リスキリングとはこのようなものだが、リスキリングとリカレント教育の違いを企業主導の取組みか個人主導のそれか、または離職を想定するかしないかという点で区別する向きもある。
しかしながら、副業や兼業に「今後のキャリア形成において、プラスになると意図的、戦略的に判断して選び取ったものか」が問われ、かつ企業と社員の関係性を示す“エンゲージメント”について「個人と組織がお互いに信頼を寄せて一体感を醸成し、双方の成長に貢献し合う関係」を望ましいカタチとするならば、わざわざ“学び直し”の区別に固執する必要もないだろう。
大切なことは、企業にとっての人材育成、社員にとってのキャリア形成、そのどちらも優れた戦略に基づき実践されることが強く求められる、ということなのだ(戦略=経営資源の選択と集中、リスク分散を実現すること)。
◇VUCAとAI時代の人的資本経営
ここで、近年ますます注目を集める人的資本経営とは、「人材を『資本』として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営」(経済産業省、2020)を指す。
まさしく「資本」とは投資の対象であり、人材という「資本」に選択と集中を大前提とした適切な投資することで、リターンを最大化しようとする経営に他ならない。
では、企業そして社員個人は、これからどのような学びに投資するべきか。
たとえば決算書や契約書の不備をチェックする(粉飾決算を指摘することも含む)のにAIの力を借りるこの時代にだ。
ここからは筆者の仮説に基づく指摘であるが、たとえば国家レベルで人材不足が問題視されているデジタル技術ひとつをとっても、引き続きその「開発」に従事するのは、どの分野においても一握りの人材である。
そして、大部分を占めるのは開発された技術を「運用」する人材(ユーザー、実務者)なのだ。
そして、とことん優れた実務者になるための出発点は、基礎学習にあると筆者は考えている。通常、基礎の習得は、守破離の段階に則った成長や成熟を通じて、いずれ再現性のある応用に転じるからだ。
では、我々ビジネスパーソンにとっての基礎学習とは何か。
ここで例えば経営大学院や、日本国内における中小企業診断士資格は、人材に対して社会人としてのキャリアアップや転職、副業、兼業もしくは独立起業を支援するための能力開発サービスを提供している。そう考えるとビジネスパーソン一般の基礎学習と言えなくはないが、ただその時に学んで終り、後は(少なくとも実務では)使わないという内容も一定程度あると聞く。
また、筆者はこれまで企業の人事担当者からこんな相談も受けてきた。
「MBAの科目を単科ではなく、合わせ技で教えてくれませんか。うちの社員にもMBAをとった社員が相応数いるのですが、それぞれ学んだ単科の知識がつながってないみたいなんですよね」
◇事業部長になるための「経営の基礎」(生産性出版)はかくして生まれた
このような要請を受けて、筆者は単科を横断する思考をもって、経営課題を解決するための、実務に使える基礎学習の範囲や学び方について仮説を立て、次世代の経営を期待される受講者とともに検証してきた。
そして、そのような思考錯誤をまとめたのが「事業部長になるための『経営の基礎』」(生産性出版)である。
但し、これはあくまでひとつの試みに過ぎないため、企業も社員個人も双方の成長に貢献するためには、学ぶべき「基礎」をバックキャスティング*を用いて、今あらためて洞察する必要があるだろう。
*パックキャスティング:未来のある時点に目標を設定しておき、そこから振り返って現在すべきことを考える方法。(コトバンク 出典:小学館)
アイベックス・ネットワーク 代表 新井 健一