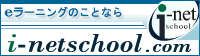※当コラムは、企業人事に従事される方にはおなじみの「月刊 人事マネジメント」に寄稿させていただいた原稿を一部加工修正したものです。
◇新入社員教育がいま意識すべき「日本型」コンプライアンス
「日本型」コンプライアンスという言葉を、お聞きになられたことがあるだろうか。
これは欧米型コンプライアンスに対して使われる言葉で、日本型の独特さを表現するものだ。欧米型が扱うコンプライアンスは通常、法令そして社内規則やマニュアル等だ。
だが、これに対して日本型は、社会規範や倫理など多くの場合、明文化されてはいないが、社会・経済活動の中で築き上げられたルールの遵守を社会(世間)から、企業から、そして消費者から求められる。また更には経営理念を企業倫理に合致させることで、はじめて理想的なコンプライアンス経営の水準に達する。
一方、欧米型が社会規範や倫理、そして経営理念など抽象的な概念を、コンプライアンスとして扱うことはない。もちろん欧米社会には、厳格な社会規範や倫理が存在するが、その範疇を扱うのは企業ではなく教会だ。欧米社会には日本社会には存在しない、いわゆる国教というものが存在する。そのため日本では、宗教にかかわる組織ではなく企業が社員の規範意識や道徳心を養うというある種のユニークな慣行に従ってきたし、利害関係者もそれを求めてきた。
だが、ここにきて日系企業の道徳教育が揺らぎ始めており、その原因は大きく3つあると筆者は考えている。
①欧米企業では標準的な「ジョブ型」という働き方が日系企業でも浸透してきたことだ。そして「ジョブ型」はあくまでも仕事を介した雇用関係であり、道徳教育などがその関係性に介在することはない。
②日系企業における管理職、少なくともその一部は、自分たちが新入社員や若手社員だったころ、上司になにを教えられたのか説明できないということだ。ゆとり世代以降、こらから社会に出る若者は「とにかくやってみよう」では動かない(動けない)。最近、就職せずにフリーランスとして社会に出ていく若者の話を聞く。本誌を購読されているような企業に就職して、先ずは3年頑張ることが、その後のキャリアにおいてどれだけの価値をもつか筆者は知っているつもりだが、当の企業人材がそれを語れなくてはならない。
③抽象的な概念を教え込むストレスだ。具体的な実務を教えるより、抽象的な概念を教えるほうが難しいし、それをするには、教える側にとっても、教えられる側にとっても相応の信頼関係が前提となる。それがなければ、簡単にハレーションが起こり、ハラスメント(無理解、いやがらせ、いじめ)で訴えられることになりかねない。
但し、日系企業が施してきた道徳教育は、(少なくとも今のところ)断片的なマナー教育を受ければ習得できるような代物ではない。したがって、日系企業において指導的な立場にある人材は、自分たちが新人や若手社員だったころ、何を学んできたのかあらためて丁寧に言語化してみる必要があるだろう。