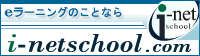※当コラムは、企業人事に従事される方にはおなじみの「月刊 人事マネジメント」に寄稿させていただいた原稿を一部加工修正したものです。
管理者のスキルとしてのバランススコアカード:4つの視点
前回ご紹介したバランススコアカードは、通常4つの視点(企業によってはより多くの視点を設定する場合もある)、すなわち「財務」「顧客」「業務プロセス」「学習と成長」の視点で職場課題の解決を図る訳だ(このフレームワークを戦略マップという)。
なお、当の解決策と共に重要なことは、各視点において講ずる打ち手が、それぞれ連動していなければならないとうことだ。
たとえば、職場メンバーの「学習と成長」が「業務プロセス」を短縮、もしくは自動化し、それが社内外「顧客」の不満足を解消、もしくは満足を向上させ、結果として売上をあげる、コストを下げる、または労働生産性を上げる等「財務」に好ましい影響を与えるという具合である。
なお、この戦略マップを描くスキルは非常の奥深いものであるが故に、習得過程で例えば次のような不具合を解消する必要がある。
①理想とする戦略マップが描けない。
②理想のマップと現実に乖離がある。
③職場課題の解決策が具体性を欠く。
④解決策が財務の視点にいたらない。
⑤描いた戦略マップが実行性に欠く。
①理想とする戦略マップが描けない。
先ず①「理想とする戦略マップが描けない」であるが、理想という抽象的な概念は、経営方針や組織目標により変わるものであると心得る必要がある。
したがって、時の上位方針や目標を丁寧に読み取り、職場としてどうしたら組織目標を達成できるのかということを4つの視点で検討する。
②理想のマップと現実に乖離がある。
次に②「理想のマップと現実に乖離がある」であるが、理想は多くの場合、直ぐに実現できるものではなく、複数年かけて実現してよいものであるならば、理想とする到達点に向けて、段階を経たマップを描くのがよいであろう。
③職場課題の解決策が具体性を欠く。
次に③「職場課題の解決策が具体性を欠く」であるが、たとえばよく「メンバーのコミュニケーションの活発化」「職場業務への精通」などという打ち手がマップに描かれることがある。
しかしながら、マップはそもそも職場メンバーの自律的なアクションとその達成を明確にするために作成されるのであるため、たとえば具体的に「誰が」「いつまでに」「何を」達成することが「学習と成長」につながるのか、最終的にはバイネームにまで落とし込むべきだ。
④解決策が財務の視点にいたらない。
次に④「解決策が財務の視点にいたらない」であるが、これは職場の管理監督者に財務知識が不足しているか、もしくは職場で解決すべき課題認識が矮小であるが故にそうなるかどちらかだろう。
そもそも営利企業活動において、財務にインパクトを与えない仕事はない。
しがたって、たとえばマップ上「学習と成長」「業務プロセス」の視点までしか描けない場合には、財務の知識を充実させるか、もしくは職場の課題認識が上位目標の達成に向けて低く見積もられていないか点検する必要があるだろう。
⑤描いた戦略マップが実行性に欠く。
最後に⑤「描いた戦略マップが実行性に欠く」であるが、これは職場メンバー個々人の自律的なアクションとその達成についてKPIが設定されていないからである。
なお、KPIはプロセス指標と業績指標を設定すべきである。
たとえば「学習と成長」の視点として、ベテラン社員から若手社員に業務の一部を移管する場合、移管を進める時間が2週間に1回2時間など、定期でしっかりと確保されているか(プロセス指標)、最終的に移管が完了して、若手社員は当該業務を独力で完遂することができるようになったか(業績指標)という具合だ。
なお、いずれの指標も数値で表せるものが分かりやすいが、獲得したい成果(プロセス+業績)によっては状態目標(理想とする成長の度合いや状態)を指標として設定してもよい。
このようにバランススコアカード、戦略マップは職場の理想的な状態を経営管理体系に落し込む手法であり、職場を管理監督する人材であれば、ぜひ身に付けておきたいスキルである。
なぜなら、このスキルが充実すれば、どんな巨大組織も動かすことができるはずだからだ。
アイベックス・ネットワーク 代表 新井 健一