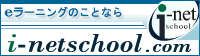※当コラムは、企業人事に従事される方にはおなじみの「月刊 人事マネジメント」に寄稿させていただいた原稿を一部加工修正したものです。
◇ヒューマンスキルを用いたリーダーシップの限界
リーダーは職場、組織、事業そして経営課題を解決しなければならない。
だが、たとえば大きな組織を預かるリーダーが、社員一人ひとりに自らの課題認識とその解決方法を伝え、動機づけ、常にメンバー個々人の業務遂行とその達成状況をチェックし、うまく進捗していなければ当該社員とともに打開策を模索する……という訳にもいかない。
◇経営管理=予算管理という誤解
リーダーは各組織、職場が成すべきことを理解し、その達成に向けて邁進することができるよう、自らの経営課題とその解決構想を経営管理に落し込まなければならない。
そのための手法は多数存在するのだが、多くの企業において予算管理制度が前面に出過ぎている嫌いがある。
だが実際、管理手法は予算制度だけではなく、目標管理制度なども当然に含まれるし、これらの手法は本来上下の関係にあるわけではなく、ある手法が他の手法を包含するわけでもないのだが、それでも多くの組織において予算管理≒経営管理として見なされているのが実状である。
なぜなら、予算が責任会計原則(管理上の効果をあげるため、会計と職制上の責任者とを結び付けること)に基づき編成・管理されるため、予算管理を経営管理の中心に据えれば、経営者にとっては(言葉を選ばずに言えば)管理が単純で樂だからだ。だが、大きく2つの理由により、それでは企業経営はうまくいかない。
理由①:数字という諸刃の刃が引き起こす暴走
先ず1つめの理由として、会計数字という指標に対する責任が殊更重く課されたり、他の指標の設定がなされなかったりすると、組織にとって重要な仕事、たとえば人材育成やコンプライアンスなどについて当該数字との連関を見出すことができず、結果軽視されるようになるからだ。
なお、時に数字という明確な指標が組織や個人を暴走させることもある。企業不祥事で世間を騒がせた中古車販売・買取会社は、事故車両を修理する工場の業績評価尺度として「@(アット)」という指標を用いていた。
もともと@とは単価を表す記号であるが、本来工場ではコントロールできない〈事故の程度〉を工場長に業績目標として課したのである。
これが工場長を「ゴルフボールを靴下に詰めて破損個所を叩いて広げる」という異常かつ不正な手法に走らせてしまった。
理由②:管理会計というスキル開発への未着手
また2つめの理由は、予算管理を所管する部門(経営企画部か経理財務部)と目標管理を所管する部門(人事部)が連携していないことから生じている。
当の人事部は目標管理やその達成を業績とした人事評価スキルを高めるため、管理職に対して研修などを実施する。
だが、いつまでたっても予算管理上の組織目標と個人目標が連動しない、うちの社員は個人目標がまともに書けないと嘆く。
これは管理職が、予算管理制度の不備を補完しつつ、組織内のマネジメント構想を経営管理に落し込む管理会計の学習に着手していないことによる。
だが、多くの企業人事は「管理会計は経営企画部か経理財務部が扱うもので、我々が扱う範疇ではない」と考えてしまうため、当該能力の開発に至らないのである。
◇予算管理を補完するバランススコアカード
このような知識やスキルのヌケ・モレを克服するために、管理職の職場マネジメント構想をバランススコアカードに落し込む訓練をお勧めする。
バランススコアカードは、1990年代初頭にハーバードビジネススクールのロバート・S・キャプラン教授と戦略系コンサルティング会社のデビット・P・ノートン氏が開発をはじめ、経営管理手法として現在進行形で変化している。
より具体的には職場構想を4つの視点、すなわち「財務」「顧客」「業務プロセス」「学習と成長」に落し込む。
その際に重要なことは、各視点の業務目標にKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)を設定し、これを体系化することだ。
これにより組織目標の達成を図りつつ、かつ人材育成などをバランスよく経営管理に取り込むことが可能となる。
アイベックス・ネットワーク 代表 新井 健一