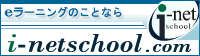※当コラムは、企業人事に従事される方にはおなじみの「月刊 人事マネジメント」に寄稿させていただいた原稿を一部加工修正したものです。
◇新入社員研修の場でおこっている学級崩壊とは
毎年、多くの新入社員研修を手がける某社・社長と、近年の新入社員について話をする機会があった。そこで彼は「学級崩壊」という言葉を使っていたが、それはたとえば、
①「挨拶」をどうしてしなければならないのか、(悪びれているわけではなく)率直に分からないから講師に聞いてくる、また、従来であればこなせてきた
②教材をこなせない、消化することができないというようなこと
これらを指してその言葉を使っていた。
それを聞いて筆者は、
①受講者の上司には、部下に対する安全配慮義務があり、部下(特に新入社員)は挨拶をもってその履行を手助けする、その認識の欠如
②情報処理能力の低下
などとあれこれ考えていた。
◇損得や作戦でメシが食える大人になる!
そして社長は、一体これから新社会人に何を教えるべきかと話を進めようとしたときに、筆者はたまたま手にしていた本を彼に見せた。
それが「メシが食える大人になる!よのなかルールブック」(花まる学習会代表 高濱正伸監修・日本図書センター)である。
これは主に小学生向けに書かれた本であるが、社長はその本をめくりながら、新入社員に伝えるべきこと「メシが食える大人になること」そのための「よのなかルールを身に付けること」という具体に合点したようだ。
「メシが食える大人になる」、これは生きていくことだ。
但し、よのなかのルールをやぶって生きていけるわけではない。
よのなかのルールをやぶっても生きていける人間がいるとすれば、よっぽど何かの突き抜けた才能に恵まれたか、法を犯したか、凡そそのどちらかだろう。
これは筆者のしがない人生経験だが、筆者には他者に誇れるような才能はない、よのなかのルールを守る事でなんとか生きていけているという具合だ。
そして、ルールというのは人を守るためにあるだけでなく、実はルールを熟知し、積極的に立ち振る舞った人を周囲が贔屓(ひいき)にし、機会(チャンス)を提供するためにある。
◇笑顔で気持ちのよい挨拶の費用対効果
何で挨拶をしなければいけないのですか、というようなご時世において、笑顔で気持ちのよい挨拶ができる新人はそうでない同期との比較においてとても目立つ。
それに社会人になってしまうと、多くの場合、仕事で成果を出したから、目立ったから(それだけで)個人が炎上するなんてこともなくなる。
一個人は、組織の一員として仕事をしているに過ぎないからだ。
社会に出てしまうと、与えられる機会も結果も平等ではない。
したがって、周囲にいかに自分“推し”を増やし、多くの機会を提供してもらうかは、自分の立ち居振る舞い(マーケティングやブランディングとも言えよう)にかかっている。
結局、新社会人は人生において損をしたいのか、得をしたいのか。
得をしたいのであれば、その出発点は、よのなかルールを知るということだ。
◇「よのなかルール」の攻略本を企業が作成し、伝える時代
一方、教える側も新社会人版の「よのなかルールブック」を理詰めで伝える必要がある。
ではよのなかルールとは何か。それは企業や社会全般を統制する倫理規範であり、当該企業の経営理念が一般的な倫理規範に「うちの会社」のという枕詞と解釈を与える。
日本型コンプライアンスという特殊な統制環境(日本国憲法における政教分離の原則により、欧米型のように倫理規範を扱う教会が存在しない社会)において、日系企業がよのなかルールを紐解き、再構築することは企業にとっても急務である。
また、新社会人も注意深くそれを吸収しなければならないであろう(いまのところ日系企業組織以外、実務とともに新社会人に道徳心までを教えてくれる先を筆者は知らない)。
この少子高齢化社会の急速な進展において、就活市場は未曽有の売り手市場であるが、よのなかルールを知る売れる人材がますます引く手あまた、そちらの側に入りたいものである。
アイベックス・ネットワーク 代表 新井 健一